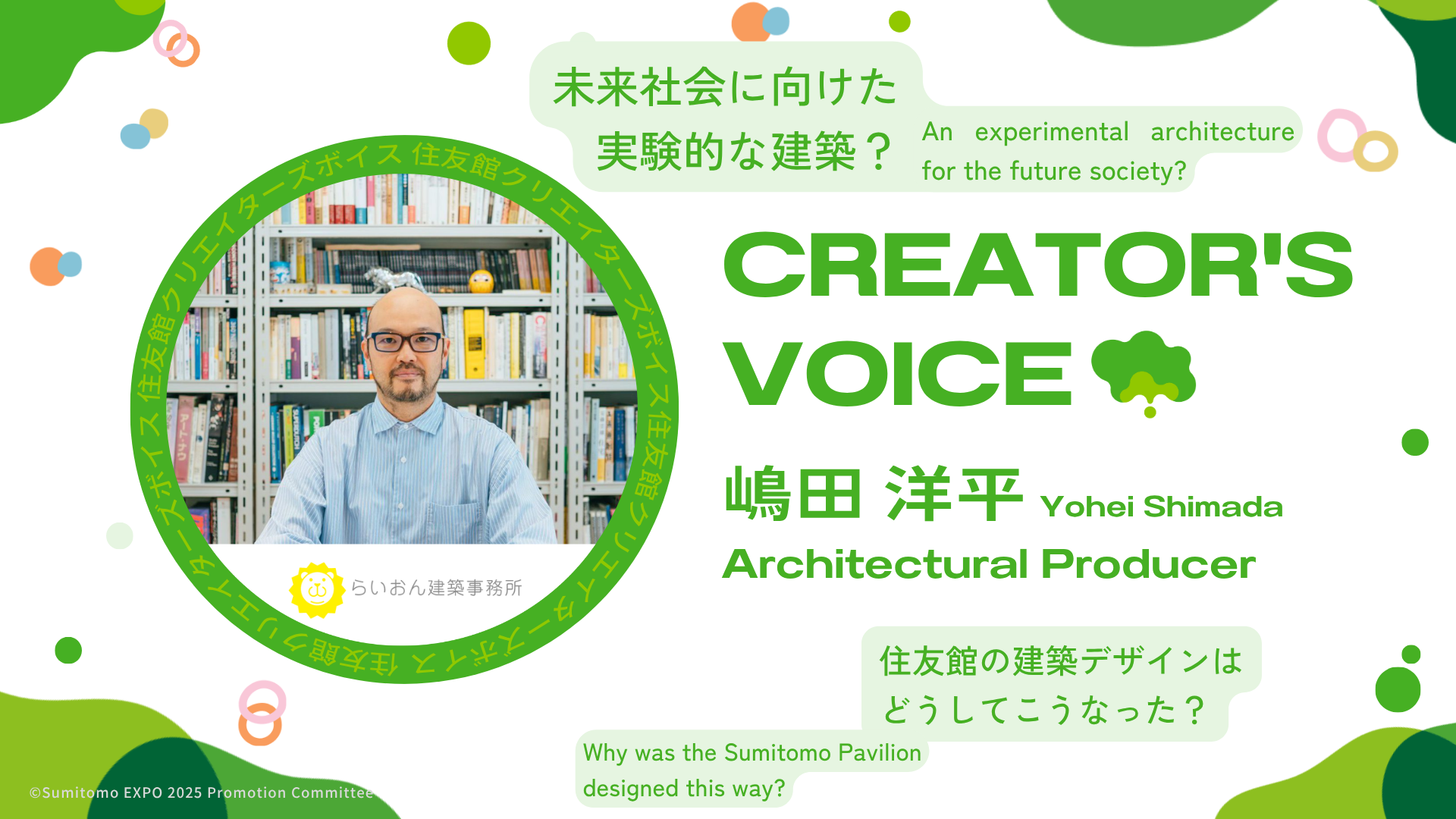
住友館クリエイターズボイス Vol.2 嶋田 洋平(らいおん建築事務所)
こんにちは、住友館です。
この連載「住友館クリエイターズボイス」では、展示や建築、演出に関わったクリエイティブスタッフたちの“声”を、少しずつ紹介していきます。
万博やパビリオンにかける想い、乗り越えた苦難、ゆずれないこだわりなど、たくさんの物語が詰まっています。
今回の語り手は、住友館の建築プロデューサー嶋田洋平さん(「らいおん建築事務所)です。
住友の森の木々1000本を用いてつくられた、ぬくもりも感じられる住友館の建築についてお伺いします。
<嶋田 洋平 プロフィール>
建築家。2001年から建築設計事務所みかんぐみに所属し、チーフアーキテクトとして愛・地球博トヨタグループ館の設計を担当した経験を持つ。現在は遊休不動産をリノベーションすることで衰退するエリアを再生するまちづくりの活動などを行う。東京・早稲田の神田川ベーカリーの経営も行うマルチなキャラ。
https://www.lion-kenchiku.co.jp/
仕事の失敗が住友館に関わるキッカケ!?
7年くらい前に仕事上の大きな失敗をしました。数年間落ち込んだ時期があって、一体自分には何ができるだろうかと悩んでいた頃、ふと頭に浮かんだのが20代後半の数年間に自分が青春を捧げた2005年愛・地球博のトヨタグループ館の仕事でした。
あの時期に得た経験やスキルが自分の大きな糧と自信になっていると改めて思い出し、すぐに当時のパビリオンに関わっていた方々に連絡をとりました。
2021年の夏、総合プロデューサーの内藤純さんに数年ぶりにお会いし、大阪・関西万博に関わらせてほしい!と直談判したところ「住友館の建築調整をいっしょにやらないか」と誘っていただきました。さらに、大阪の地で住友グループのパビリオンに関われるという幸運、嬉しくて二つ返事でお引き受けしました。
未来社会に向けた実験的なパビリオン建築
この仕事に携わりながら、住友グループが別子銅山の開発を礎として培ってきた長い歴史の中でどのような想いで事業を発展させてきたかを学びました。
近代の大規模な開発による負の側面として荒れ果ててしまった別子の山々に木々を植えて森を再生させたという事実、自然や環境に対する住友グループの姿勢を、博覧会という祝祭の場でパビリオンの建築としてどのように表現するのか、という大きな課題がありました。

博覧会パビリオンは半年間の会期を終えれば解体される運命ですが、逆の言い方をすればたった半年間、雨風を凌いで安全に建っていてくれればよいともいえます。このことは、竣工後に何十年も使うことを前提に建てられる建物とは全く異なる耐久性能で良いことを意味します。
だから、パビリオン建築そのものも「未来の社会への実験」としてデザインされるのです。半年間だからこそできる実験。そこに住友の森の木々を掛け合わせることで住友館の外観デザインはできています。70年の大阪万博の年に植林したスギや、先人たち植えたヒノキを伐採して合板を作り、それを用いて建物の外観を作ることにしました。

通常、合板を建物の外壁にすることはできません。都市部では火災の危険性から燃えやすい木をこれだけ大規模な建物の外壁にすることは法律で禁止されています。また建物の中の人や財産を守るという観点から風雨で劣化しやすい木材だけで外壁を作ることは技術的に非常に難しいため避けるのが一般的です。住友館はまさに「博覧会の会場で半年間」というお祭りならではの条件だからこそできる”建築の実験”となりました。
お客様はパビリオンの中に入ってUNKNOWN FORESTで様々な体験をすることになりますが、最初に目にするのは住友館の外観です。外観はシンプルで幾何学的で未来的な印象があるのに、素材はとても馴染みのある合板ベニアでできているため、暖かさや親しみやすさを感じていただけると思います。シャープかつ近未来的でありながら、なぜか懐かしい印象のパビリオンになっているのではないでしょうか。建物内の展示空間とのギャップもあります。
おそらくこれだけの規模の合板でできた建物を人々は見たことがないと思いますので、お客様にもきっと初めての体験になるのではないかと思っています。

万国博覧会を開催した意義を感じるようになった
開催前は、何かとネガティブな印象の報道がされていた今回の万博ですが、開幕後に実際に会場にお越しいただいて体験されたお客様からの反応はとても良い情報が多く、この仕事に関わった者として非常に安心しました。実はこっそりとSNSで「住友館」のことをエゴサーチすることがあるのですが、とにかく住友館の評判が良くて、嬉しく思っています。
前回の万博から55年が経ち日本も成熟した国になりました。海外旅行をすることがそれほど難しくない時代になり、インターネットを通じていつでも世界に繋がることができます。そんな中で国際博覧会をこれだけのお金をかけて日本で開催することの意義は何なのかが強く問われていると思います。
今回、博覧会が開幕してたくさんの方達が会場を訪れた体験や感動をSNSを通じて発信している様子を見て、どんなに技術が発達し成熟しても、人と人がリアルに繋がる空間と場はより一層に価値を持つのだと改めて感じました。
世界を旅してみると、日本の魅力に改めて気付かされることが多いです。
食文化の豊かさやクオリティ、安全で衛生的な都市での暮らし、季節の移り変わりを感じる美しい風景。一つ一つが全て世界に誇れるコンテンツだと思います。その魅力を体験するべく、今、世界中から多くの人たちが日本を訪れているのだと思います。
そんな中で開催された今回の万博において、日本の国や自治体や企業が様々な文化や取り組みや最先端技術や考えを、世界の人たちにリアルな空間で紹介しています。僕自身、はじめて知った日本の農業や林業分野での新しい取り組み、日本の企業や研究者たちが持つ最先端の技術、地方での豊かな生活文化など数え上げたらキリがありません。
海外から日本を訪れる外国人の方達に今の日本をさらに深く知っていただくこと、これだけ情報が溢れ、技術によっていつでもどこでも世界中と繋がることができる時代に同じ場所でリアルに人と繋がることができること。この二つが博覧会の意義だったのではないかと感じるようになりました。
ここを読んでいるみなさんに、ひとこと
万博にお越しになる際は、ぜひ東ゲートからお入りください!
ゲートをくぐり抜けて会場に入れば、祝祭空間の高まる高揚感に合わせて住友館が姿を現します!世界でも例のない全て木材合板でできた屋根と壁をもつ大規模なパビリオン建築の外観をぜひご覧になってください。




